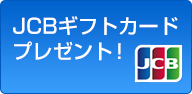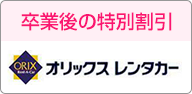雪道運転のコツと気をつけるべきポイントを教習所が解説
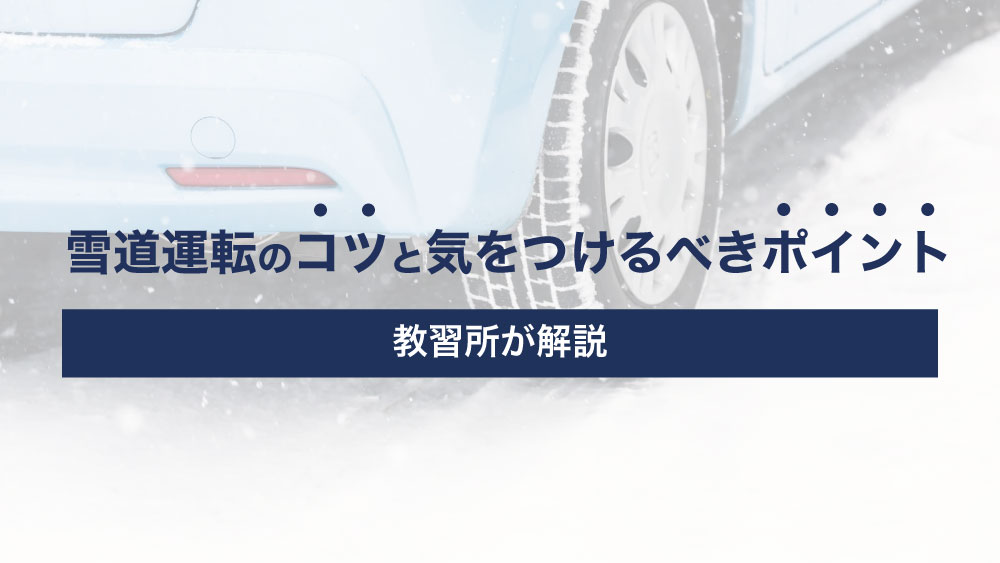
雪道の運転は事故につながりやすいのが特徴です。
雪に慣れていない都市部に住む方はもちろん、雪が積もりやすい地域に住む方でも雪道を運転するのは危険です。
この記事では、雪道を運転する基本的なコツと、気をつけるべきポイントを解説していきます。
雪道運転の4つのコツ
雪道を運転する時の基本的なコツは、以下の4つです。
コツ1:急な操作をしない
雪道では、急ブレーキ、急発進、急加速、急ハンドルなどの「急」な操作はNGです。
車が発進する時は、普通の路面では駆動輪がほんの少し空転し始めたタイミングで、タイヤと路面の間に摩擦力が生まれ、車体が前に進みます。
しかし、雪道や凍結した路面では、摩擦力が極端に少ないため、「ほんの少しの空転」ですぐにスリップしてしまいます。
そのため、アクセルはゆっくりじっくり踏み込み、駆動輪を空転させないように発進しなければなりません。
また、雪道は滑りやすく、制動距離が長いため、ゆっくり丁寧にブレーキを踏む必要があります。
急ブレーキを踏むと、タイヤがロックしてしまい、ハンドルも利かないまま、スリップしてしまうため注意が必要です。
また、カーブなどで急ハンドルを切ると、タイヤのグリップが効かず、曲がることができません。
雪道や滑りやすい凍結路面では、ハンドルが真っ直ぐな状態でまずブレーキを踏むことが大切です。
十分に減速したらブレーキから足を離してハンドルをゆっくり切り、ハンドルを戻してからアクセルを踏みましょう。
コツ2:エンジンブレーキを使う
雪道では、ブレーキが利きにくく、ABS(アンチロックブレーキシステム)が作動しやすいです。
ABSは多用するものではないため、できるだけ早くアクセルから足を離すことで、エンジンブレーキを作動させましょう。
エンジンブレーキを使ってある程度減速してから、ブレーキをゆっくり踏み込めば、スリップしにくくなります。
コツ3:事前にブレーキをチェックする
雪道を走る時は、事前にブレーキの利き具合をチェックしておくと良いでしょう。
周りに人がいない安全な場所で、ごく低速でブレーキを踏み、制動距離や滑り具合を確認します。
事前に制動距離や滑り具合を確認することで運転し始めてからも、どの時点でどれくらいブレーキを踏んだ方がいいのかがわかります。
コツ4:車間距離を十分に取る
雪道では、制動距離が長くなるため、普段の2倍以上の車間距離を取るようにしましょう。
前の車の制動に気を配り、前の車がブレーキを踏んだら、こちらもブレーキを踏むようにします。
雪道の運転で気をつけるべき5つのポイント
雪道で、特に気をつけるべきポイントは、以下の5つです。
ポイント1:アイスバーン
アイスバーンは、雪が解けて凍結した状態で、氷のようになっています。
滑りやすく止まりにくい、極めて危険なポイントなので注意が必要です。
特にアイスバーンになりやすいポイントは、以下の5つです。
- 交差点
- 日陰
- カーブ
- 橋の上
- トンネルの出入り口
交差点は、交通量が多く、車が停車と発進を繰り返すため、圧雪されて路面が鏡のようになったミラーバーンがよく見られます。
右左折の際には、十分にスピードを落とすようにしましょう。
日陰やカーブは、積もった雪とアイスバーンが混ざり合っているところが多いです。
橋の上は、吹きさらし状態で、全方向から熱が奪われるので、ほぼアイスバーンになっています。
トンネル内は雪がないため、スピードを出しがちですが、出口はアイスバーンになっていることが多いです。
出口近くになったらスピードを落としましょう。
また、「ブラックアイスバーン」と呼ばれる、ただの濡れた道にしか見えないアイスバーンもあるので、注意しましょう。
ポイント2:ホワイトアウト
地吹雪などで、視界が極端に悪くなることをホワイトアウトと言います。
ホワイトアウトになった状態では、できるだけ運転を控えるのが一番です。
もしも運転している時にホワイトアウトになった場合は、ハザードランプを点灯して、ブレーキをゆっくり踏んで少しずつ減速し、安全な場所に一時停車しましょう。
ポイント3:新雪が積もったばかりの道路
新雪が積もったばかりの道路では、歩道や側溝との境界線が見えにくくなります。
そのため、左寄りで走行すると、縁石にぶつかったり、側溝にはまったりすることがあるため注意が必要です。
新雪の道路では、なるべく中央寄りで走りましょう。
新雪にはまった場合は、ゆっくりと車を前後に動かして、タイヤの周りの雪を踏み固めるようにします。
ポイント4:わだちの跡がついた道路
わだちの跡がついた道路は、雪が多いほど高低差ができています。
そのため、無理な車線変更などわだちに逆らって走行すると、ハンドルを取られたり、スピンしたりする可能性があります。
わだちの上を走る分には、スリップなどのリスクが低く、比較的安全に走行できるので、わだちに逆らわず、その上を走るようにしましょう。
ポイント5:坂道
坂道は、雪が積もると雪山と同じになります。
上りは、平坦なところで助走をつけ、急加速せずにアクセルを一定にして走りましょう。
下りは、いつでも停まれる速度にまでスピードを落とし、エンジンブレーキを使いながら走るじことが大切です。
雪道を走る前に準備しておきたいもの
雪道を走る前に最低限準備しておきたいものは、以下の5つです。
| スタッドレスタイヤ チェーン ジャッキ |
平成30年の新たなチェーン規制により、大雪の時にはスタッドレスタイヤを履いていてもチェーンを取り付けていないと通行止めになる可能性があります。 |
|---|---|
| 寒冷地用のウォッシャー液 | 寒冷地用のウォッシャー液は、通常のものよりも濃くなっていて、凍結しにくいのが特徴です。寒冷地用のウォッシャー液は通販で購入することが可能です。 |
| ブースターケーブル | 寒冷地ではバッテリーが上がりやすくなります。そんな時にブースターケーブルがあれば、他の車とつないでバッテリーを回復できます。 |
| 毛布 | 何かトラブルがあって車中に閉じ込められた場合、毛布があると重宝します。 |
| 飲み物 | 特にトラブルに遭った時には、飲み物がないと生命の危険にさらされてしまいます。雪道を運転する際は、ペットボトル飲料などを荷室に入れておくのもおすすめです。 |
このように、スタッドレタイヤやチェーン、ジャッキのように必須なものの他にも、毛布などあると便利なものも準備しておくと何かあった時に安心です。
余裕を持って揃えておきましょう。
雪道運転でトラブルに遭った場合の対処法
トラブルに遭った場合の対処法は、以下の4つです。
<1>安全な場所に停車する
ホワイトアウトなどで視界が確保できない場合、スリップや立ち往生して走行が続けられない場合は、周囲の状況を確認し、ハザードランプをつけて一時停止しましょう。
ハザードランプをつけていないと他の車に停車しているのが見えないため、必ず点灯します。
また、視界が悪い場合は発煙筒や三角停止板を活用するのも一つの方法です。
<2>車内での安全を確保する
何かトラブルがあって車内に待機している時、排気管に雪が積もると一酸化炭素中毒になる可能性があります。
そのため、排気管の周りだけでも必ず除雪するようにしましょう。
除雪している間も車内温度を維持し、毛布や衣類などで寒さをしのぎます。
もしもエンジンを切る場合は、体温が低下しないように工夫しましょう。
<3>タイヤ周辺を除雪する
立ち往生した場合、最初にタイヤ周辺を除雪しましょう。
シャベルや足で雪を固め、タイヤが地面を掴みやすい状態を作った後は、アクセルを静かに踏み込みます。
急な発進は状況が悪化するため避けましょう。
<4>外部に連絡する
自力での脱出が難しい場合は、JAFや保険会社のロードサービスに連絡しましょう。
その際は、GPSやスマートフォンを利用して現在地を正確に伝えます。
また、 除雪作業が必要な場合は道路管理者や警察に連絡し、対応してもらうことが重要です。
雪道は万全の準備をして安全運転しよう!
雪道を走るのはリスクが高いものです。
そのため、雪が積もっている間は運転をしないのが一番です。
どうしても雪道の運転が必要な場合は万全の準備をして運転しましょう。
雪道はアイスバーンやホワイトアウトの可能性もあり危険です。
運転する際は十分にスピードを落として安全運転しましょう。